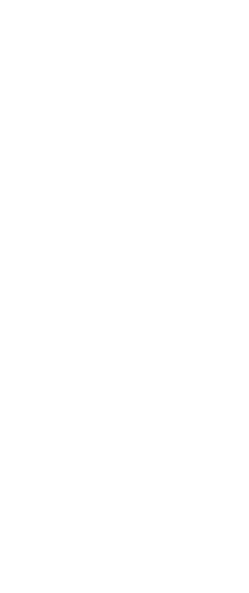寺の屋根には歴史が宿る
杲洞寺の建築には想いが宿る
お寺の過ごし方は人それぞれですが、どの時代においても、精緻な彫刻や繊細な装飾、静謐な空間が織り成す美が人々の心を打ち、深い信仰を集めてきました。これらの建築や飾りは仏教の教えを具現化したものであり、時を超えて受け継がれ、今も多くの人々に深い感銘を与え続けています。
お寺の過ごし方は人それぞれですが、どの時代においても、精緻な彫刻や繊細な装飾、静謐な空間が織り成す美が人々の心を打ち、深い信仰を集めてきました。これらの建築や飾りは仏教の教えを具現化したものであり、時を超えて受け継がれ、今も多くの人々に深い感銘を与え続けています。

杲洞寺の本堂は元々茅葺屋根が特徴の古き良き造りでしたが、耐震や環境整備の為、2009年に新たな姿へと建て替えを行なっております。多くの方がこの工事に携わり、そこには人間と同じ数のドラマ、こだわり、そして想いがあります。


両端の曲線は職人がこだわりにこだわった箇所です。丸瓦と平瓦を交互に並べてふくのが〝本瓦葺〟。
一方、江戸時代から横断面が波形(S字形)の平瓦でふいたものを〝桟瓦葺〟といって民家で多く用いられています。


社殿・仏殿の正面に張り出しており、〝礼拝所〟という意味です。また、殿堂にのぼる階段のところで、寝殿造りの階隠(ハシカクシ)に相当し、向拝の内側の斗に手挟がおかれ、正面に墓股(カエルマタ)をおくのが一般的とされています。


花頭窓(かとうまど)は、上部が花や葉のような曲線を描いた装飾的な窓で、灯明用瓦器に似ているからとも。美しいデザインが建築に華やかさを加え、自然との調和を表現しています。


鬼瓦(おにがわら)は、日本の伝統的な屋根瓦で、鬼や神像を形取った装飾が特徴です。屋根の端に設置され、その建物を魔除け・厄除けし、守護すると言われています。
鬼瓦のかわりに鴟尾(しび)といって、魚尾形の飾りがあり、変形したのが名古屋城のシャチホコです。








178年間親しまれた旧本堂。
岩崎山の花崗岩の岩盤上に建てられ、屋根は大部分が茅葺で、県内でも珍しい寄棟造りの茅葺屋根の本堂でした。
残念ながら、茅葺技能者の減少や茅葺材の入手難から茅葺き屋根の維持が困難となり、新本堂再建のため、2007年に取り壊しを行いました。


内陣(ないじん)は、寺院や仏堂の中で、最も神聖な場所です。通常、本尊や仏像が安置されている区域で、僧侶が法要を行う場所として使われ、仏の世界そのものとも言われています。
須弥壇(しゅみだん)とは、
仏教の寺院などで仏像を安置するための
壇(だん)のこと。


須弥壇(しゅみだん)は、仏教寺院において本尊や仏像を安置するための壇(台)であり、須弥山(しゅみせん)に由来しています。杲洞寺では龍の欄干からその高さに至るまで、細部まで趣向を凝らした特別な須弥壇をご覧いただけます。


本堂の天井から吊り下げられた黄金色に輝く吊り物〝天蓋〟。
インドで僧侶や仏像を日光や雨から守るための傘を象徴・装飾化されたものです。


杲洞寺の山門は、ちょうどくぐり抜けると
まっすぐ本堂の中に安置しているご本尊、薬師瑠璃光如来が臨めるように設計されています。
当寺の境内に入った瞬間から、ご本尊の力、ご利益を感じていただけますように。


大晦日の夜には、檀信徒の皆様やご近隣の方々にお越しいただき、煩悩の数とされる108回、除夜の鐘を撞いていただきます。
人間は多くの煩悩を背負って生きています。眼・耳・舌・鼻・身・意の6つの感覚器官には快、不快とそのどちらでもない3つ(楽・苦・捨)があり合計18。それに好・悪・平の3種があり、これも18で合計36となる。これらにそれぞれ過去、現在、未来があり、全部で108となります。