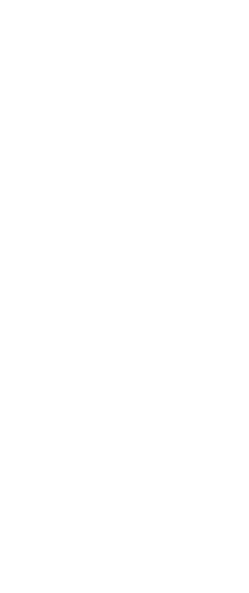四季折々の祈り織りなす
心の旅をお寺で
お寺の年中行事は、単なる儀式にとどまらず、私たちの心に静けさと深い安らぎをもたらし、日々の喧騒から解放される貴重な時間となります。
季節ごとに行われるこれらの伝統的な行事を通じて、仏教の教えを身近に感じ、心の平和を育んでいくことが大切です。
お寺の年中行事は、単なる儀式にとどまらず、私たちの心に静けさと深い安らぎをもたらし、日々の喧騒から解放される貴重な時間となります。
季節ごとに行われるこれらの伝統的な行事を通じて、仏教の教えを身近に感じ、心の平和を育んでいくことが大切です。
一月(睦月)
三が日の内にお寺へお参りに行くのが一般的です。新年を清め、その一年を良いスタートにする為の大切な行事です。心静かに祈願しましょう。
国家安泰や家内安全、無病息災などを祈願する法要です。読経によって智慧と福徳を授かるとされ、厄除けや開運のご利益があると信じられています。
二月(如月)
三月(弥生)
先祖供養を行う仏教行事です。太陽が真西に沈むこの時期は、あの世(彼岸)とこの世(此岸)が最も近づくとされ、ご先祖様への感謝と供養の気持ちを表す大切な期間です。
四月(卯月)
お釈迦様の誕生を祝う行事で、花で飾られた花御堂に誕生仏を安置し、甘茶をかけてお祝いします。命の大切さや感謝の心を育む行事として、多くの寺院で行われています。
五月(皐月)
六月(水無月)
七月(文月)
お盆やお彼岸に各家庭を訪れ、仏壇の前で先祖供養の読経を行います。
八月(葉月)
供養されず苦しむ霊(餓鬼)に食べ物や読経を施し、成仏を願いながらあわせて先祖供養も行い、家族の安穏や自身の功徳を願います。
お盆の最後に船でご先祖様をお送りします。当寺では、本堂の前に船を積み上げ見送るという行事に変わっています。
お盆の最後に船でご先祖様をお送りします。当寺では、本堂の前に船を積み上げ見送るという行事に変わっています。
九月(長月)
太陽が真西に沈むこの時期は、あの世とこの世が近づくとされ、ご先祖様への感謝と供養を行います。墓参りや仏壇での読経が一般的です。
十月(神奈月)
十一月(霜月)
十二月(師走)
大晦日の夜には、檀信徒の皆様やご近隣の方々にお越しいただき、煩悩の数とされる108回、除夜の鐘を撞いていただきます。