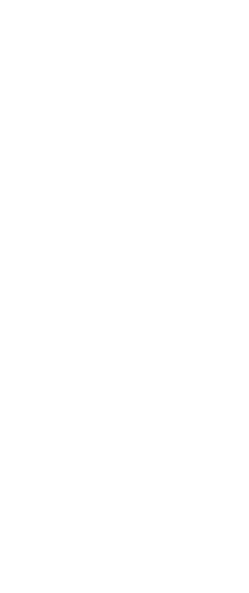今も昔も人は祈り捧ぐ
慈愛の微笑みに頭を垂れる
杲洞寺には、本尊〝薬師瑠璃光如来〟をはじめ、さまざまな仏像をお祀りしています。それぞれの仏像には深い意味とストーリーがあり、それら背景を知ることで、視覚のみでなく、さらに深く仏教の歴史と教えを理解することができます。
杲洞寺には、本尊〝薬師瑠璃光如来〟をはじめ、さまざまな仏像をお祀りしています。それぞれの仏像には深い意味とストーリーがあり、それら背景を知ることで、視覚のみでなく、さらに深く仏教の歴史と教えを理解することができます。

杲洞寺のご本尊、薬師瑠璃光如来。
人々の病や苦しみを癒し、心身の健康と幸福をもたらす仏様であり、瑠璃色に輝くそのお姿は清浄と癒しの象徴とされ、現世利益の仏として古くから信仰されています。十二の大願を立て、あらゆる苦悩から衆生を救済し、安らぎと希望の光を与える慈悲深い存在です。

山門をくぐると、ちょうど本堂にお祀りしている薬師瑠璃光如来のお姿が見えるよう、緻密に設計されています。

薬師瑠璃光如来や大医王仏ともよばれているように、東方瑠璃光世界の教主で、人間の病苦を癒し内面の苦悩を除くなど、十二の誓願をたて衆生の病苦や暗黒を救う如来です。これは四〜五世紀ごろに成立したと考えられ、日本においても七世紀頃から盛んに祀られるようになりました。
薬師如来像は、像の光背に六体の化仏(衆生済度のため別の姿にあらわれた変化の仏)があるのは、薬師如来が七つの分身をもつ七仏薬師だとされることを示しています。
薬師如来像は、釈迦如来像と同様に単独でも作られる場合もあるが、右に日光菩薩、左に月光菩薩を配する「薬師三尊像」として制作されることが多く、杲洞寺には高さ三十センチ程の坐像の薬師三尊像を祀っています。
〝内の苦しみを癒す光〟
月のような穏やかな光で、心の苦しみや迷いを癒す存在。
涼やかな月明かりが心を鎮めるように、内面の平安と静けさをもたらします。
〝外の苦しみを癒す光〟
太陽のような明るさで、病を照らし払い、生命力を与える存在。
日の光があらゆるものを平等に照らすように、無差別の慈悲で衆生を救います。

十六羅漢は仏教の教えを深く悟り、解脱を得た16人の聖者です。彼らは仏陀の教えを守り広め、苦しみを解消する力を持つ存在として信仰されています。個性豊かな姿で描かれることが多く、それぞれが異なる教訓を伝えます。
羅漢は梵名アルハンの書字で「阿羅漢」の略で導敬をうける人の意味です。即ち仏道を修行して迷いの世界を脱し、煩悩を断ち切り、人びとの供養をうけるのに相応しい境地を得た人のことを言います。

羅漢は梵名アルハンの書字で「阿羅漢」の略で導敬をうける人の意味です。即ち仏道を修行して迷いの世界を脱し、煩悩を断ち切り、人びとの供養をうけるのに相応しい境地を得た人のことを言います。
十六羅漢は、原始仏教では仏陀をさす場合もありましたが、大乗仏教がおこってからは小乗仏教における聖者をさすことになりました。
特に十六羅漢は、永久に生存して末世において滅びる仏法をおこすように委嘱されたと考えられ、篤い尊信を受けるようになりました。

このうち第一尊者を「賓頭盧尊者」とも呼びますが、神通力に優れすぎ、仏陀に叱られて、南方で衆生済度につとめたと伝えられます。
この像は、日本の寺では本堂の外陣の前縁におかれ、病人が患部と同じ箇所をなでて病気回復を祈願する風習が盛んでした。
つるつるの頭を「おびんずる」と言うのはここから由来しています。


観世音菩薩立像(お恵み観音)
建立 昭和三十四年二月
犬山市にある〝桃太郎神社〟の印象的な像を製作した仏師、浅野祥雲によって作られ、現在も多くの方の信仰を集めています。
昭和三十三年三月十四日、全国百観音巡拝が終わり多年の念願が成就された喜びや感激を何かの形で残したいとの巡拝者一同の想いから観音立像の建立となりました。
札所巡拝が出来なかった方々にもご縁を結んでいただけるよう、千体観音を台座下の部屋でお祀りしています。